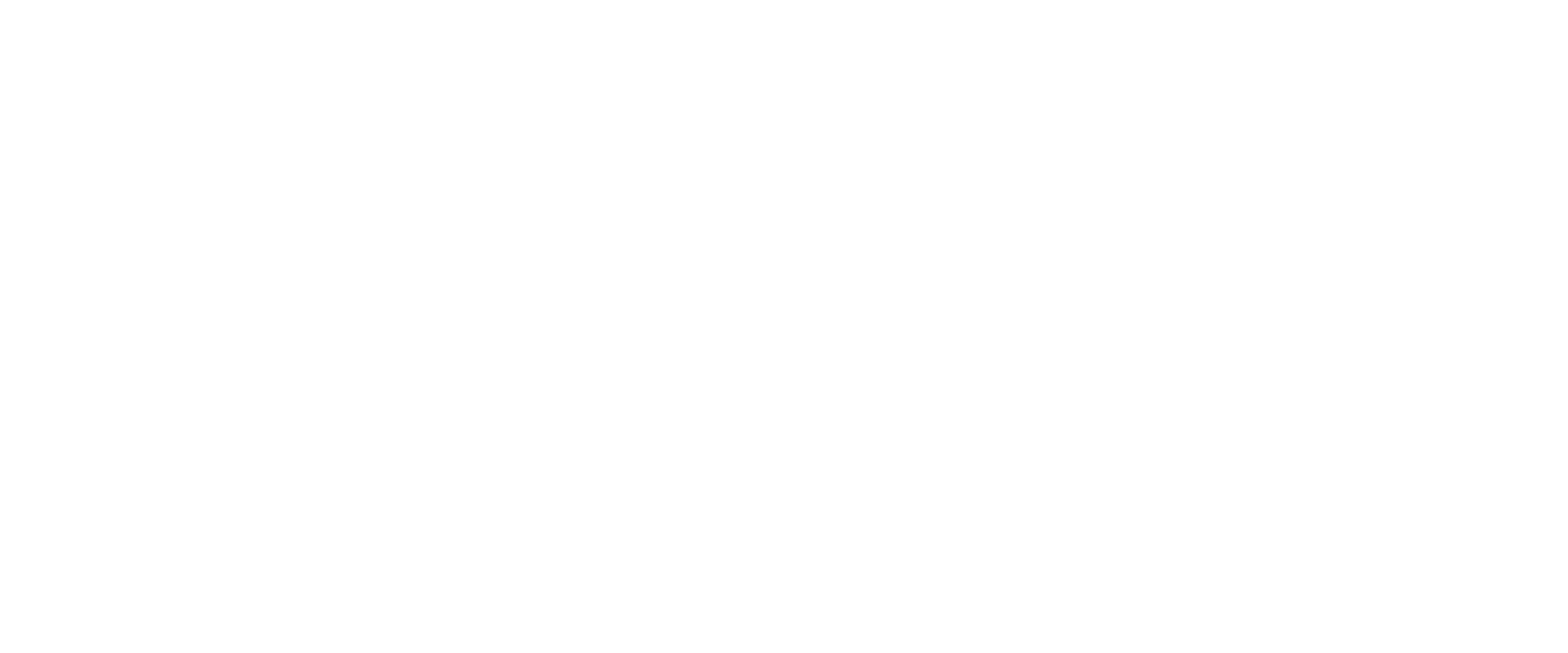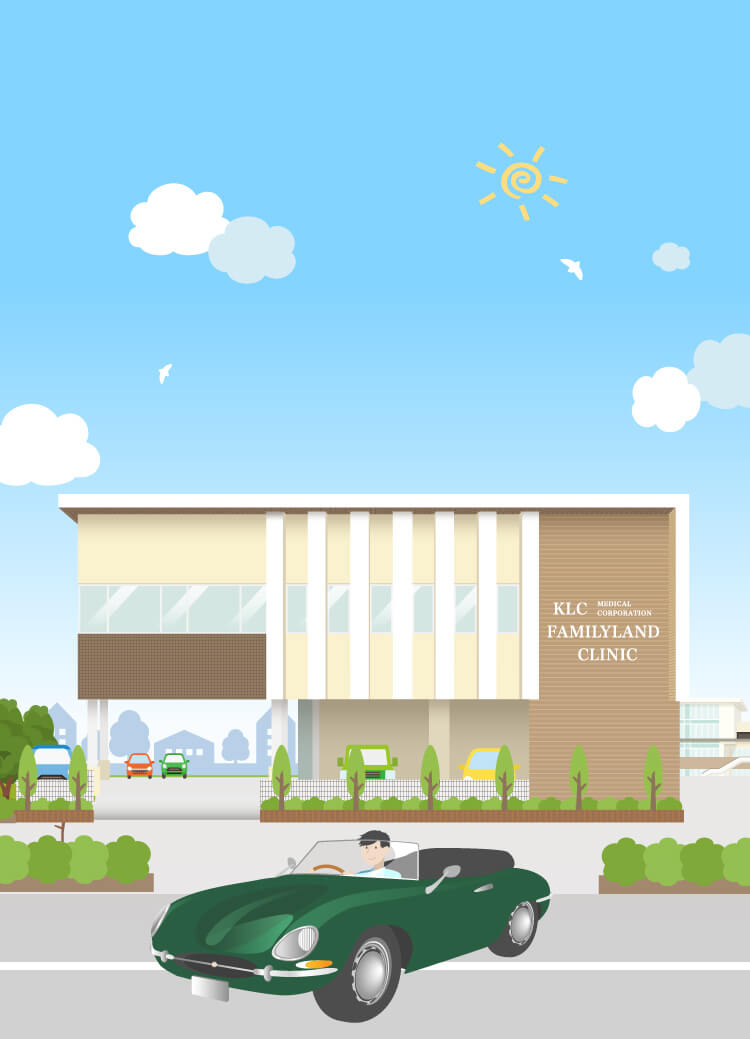What's New
-
- 2024.04.03
- 皮膚科院長を募集しています!
-
- 2024.04.03
- LINEアカウントが新しくなりました!
-
- 2024.04.01
- 「2024.4月感染症情報」
-
- 2024.03.29
- 令和6年度以降のコロナワクチン接種について
-
- 2024.03.27
- 5種混合ワクチンのWEB予約開始について
-
- 2024.03.27
- 小児肺炎球菌ワクチンについて
-
- 2024.03.25
- 名古屋市在住の方 5種混合ワクチン接種開始について
-
- 2024.03.25
- アデノウイルス検査について
-
- 2024.03.18
- LINEアカウントが変わります!
-
- 2024.03.09
- 小児科診察のお知らせ
-
- 2024.02.28
- 「子宮頸(けい)がんワクチン接種機会を逃した方へ」
-
- 2024.01.22
- 自宅や他院でインフルエンザ、コロナの検査をされて当院を受診される方へ
-
- 2023.12.20
- 小児科診察のお知らせ
-
- 2023.12.04
- 価格改定のお知らせ
-
- 2023.11.10
- キャッシュレス決済がご利用いただけるようになりました
-
- 2023.09.21
- アンケート結果報告
-
- 2023.08.21
- 小児定期予防接種の電話予約について
-
- 2023.08.07
- 8/21(月)の診察から内科Web予約が始まります!
-
- 2023.04.28
新ホームページを公開しました。今後ともよろしくお願いいたします。
-
- 2023.04.15
- 小児の原因不明の急性肝炎 続報
-
- 2023.02.08
- Web画面より受付の進行状況が確認できます